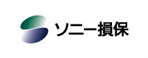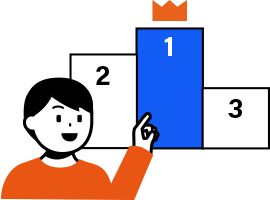自動車保険の基礎知識
シニア・高齢者でも加入できる自動車保険ってあるの?

年齢が65歳以上になっても自動車に乗る場合に気を付けることは? 年齢が上がるに従いリスクが変わるので他人に迷惑をかけないように、契約する自動車保険も吟味してはいかがでしょうか?
65歳以上でも入れる自動車保険はあります
自動車保険は、65歳以上の方でも加入することは可能です。しかし、年齢があがると、事故率が高まる傾向にあり、その影響で40代や50代の方よりも保険料が高くなるのが一般的です。年を取るとともに、事故を起こす確率は高くなるのは自然なことなので、事故を未然に防ぐために運転を評価する機器が付いている自動車保険を選ぶ考え方もあります。普段から自分の運転を評価してもらうと、スピードの出しすぎや急ブレーキ、急発進などに配慮できるのではないでしょうか。
また、ドライブレコーダーは自分で購入して設置することもできますが、自動車保険の契約をすると、ドライブレコーダー※が付与されるケースもあります。その場合、事故を起こすなど、何らかの異常を感知すると、保険会社のコールセンターに自動的につながって、「どうしましたか?」などを問いかけてもらえます。年齢とともに不安が高まる運転だからこそ、自動車保険の機能を活用して、いざという時に備えてはいかがでしょうか?
高齢者の事故は減少傾向にありつつも、高齢者ならではの特徴があります
75歳以上の高齢者が起こす死亡事故に限っては、免許人口10万人当たりの件数推移を見ると過去10年間で減少傾向です。ただ、高齢者が起こす死亡事故の特徴には特徴があり、車両単独による事故が多く、具体的には工作物への衝突や路外逸脱(斜線外へのはみ出し)の割合が高くなります。また、よく報道されるブレーキとアクセルによる踏み違い事故は、75歳未満が全体の0.5%に過ぎないのに対し、75歳以上の高齢運転者は7.0%と各段に高くなります。
(出典:https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r02kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_01_3.html)
年齢条件を活用することも考えましょう
高齢者になっても運転をする場合は、「年齢条件」の特約をつけることも考えてみましょう。年齢条件は、運転者の年齢を●歳以上と指定することで、保険料を抑えることができる特約です。たとえば、全年齢が運転できる契約にすると保険料が高くなるのに対し、21歳未満不担保、26歳未満不担保など、年齢条件を付けると、保険料を抑えられます。逆に高齢者が運転をする場合で、その車を家族全員が運転しているといった場合は、指定できる年齢を30代や40代など、世帯の中で保険料の安い世代の方に合わせると、保険料を抑えられるわけです。
保険加入の検討は直接話ができる代理店に相談してみましょう
自動車保険への加入を検討している方は、保険代理店に直接相談してみることをおすすめします。インターネットを利用して加入するのも良いのですが、自動車保険についての知識が乏しい場合、有利になる特約の存在に気づきにくい傾向がみられるからです。割引制度をフルに活用するには、プロのアドバイスを受けるのが向いています。実際に対面での相談をすれば、その場で疑問が解決できるだけでなく、担当者の人柄もつかめますので、その後のサポートについても不安なく、お任せできるのではないでしょうか。
ファイナンシャルプランナーによるコメント
65歳以上になったからと言って、自動車保険の加入を断られるわけではありません。とはいえ、高齢ドライバーは、工作物への衝突や斜線のはみだし、逆相などの“単独事故”を起こすリスクが高く、若かった時と同じ気持ちで運転するのはキケンです。運転者本人が気を付けるのはもちろんですが、自動車保険の付帯サービスなどを使って、見守ってもらう方法もあります。たとえば、保険会社のコールセンターと自動的につながっているドライブレコーダー付きのプランに加入すると、万が一、事故を起こしてしまった時の対応が速やかです。また車はサポート機能が付いているサポカーに乗り換えるなどして、安心への投資も検討してはいかがでしょうか。

| 監修者 | 畠中 雅子 (はたなか まさこ) |
|---|---|
| Webサイト | ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ |
| SNS | |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。 |