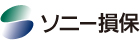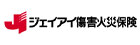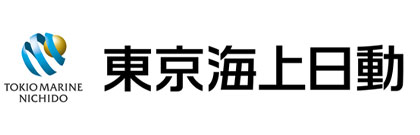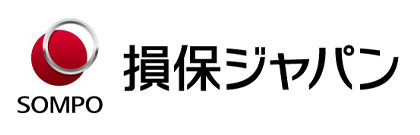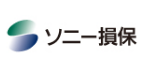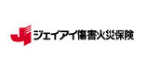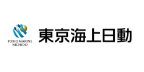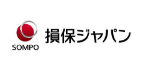火災保険の基礎知識
賃貸物件における火災保険の必要性と選び方ガイド
マイホームだけではなく、賃貸物件に住む場合でも、火災保険は重要な役割を果たします。火災保険は所有物件に住む方の家財や建物を守るためだけでなく、賃貸物件に住む方の家財を守るためにも必要となる保険だからです。この記事では、賃貸物件における火災保険の基本的な知識、必要性、選び方について詳しく解説します。

賃貸物件における火災保険の基本
賃貸物件に住んでいる場合、建物はご自身の所有物ではないので火災保険は不要と考える方もいるようです。ですが、賃貸契約を結ぶ際は、賃借人用の火災保険に加入するのが一般的になっています。建物自体は、オーナーが火災保険をかけますが、室内にある家具や日用品などは自分で保険をかけておかないと、火事などで被害を受けた場合に、補償されないからです。賃借人が加入する火災保険の主な補償内容は、「部屋にある家財の補償」と「物件の持ち主(大家さん)への賠償補償」「近隣住民への賠償補償」の3つに分けられます。
賃貸物件での火災保険の役割
賃貸物件における火災保険の主な役割は、以下の通りです。それぞれ詳細を見ていきましょう。
部屋にある家財の補償
家具や家電などの損害をカバーします。火災や水害、盗難などによって家財が損害を受けた場合に、補償されます。自身が火災を起こしてしまったとき、水濡(ぬ)れ被害にあったとき、何かを落としたりぶつけたりして破損してしまったときなど、自分の部屋の家財に損害が生じた場合、家財を守るためにも家財の補償が必要です。なお、家財補償の対象外のものもあります。下記が一例となりますが、詳細は保険会社にご確認ください。
- 1.自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品
- 2.現金、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物(通貨、預貯金証書は盗難の場合に限り補償の対象となります。)
- 3.クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
- 4.動物および植物
- 5.商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
- 6.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
- 7.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
- 8.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
物件の持ち主(大家さん)への賠償補償
賃貸物件に住んでいるあいだに火災や水漏れを起こしてしまい、大家さんや他の賃借人に損害を与えた場合、賠償責任を負うことになります。このリスクをカバーするのが「借家人賠償責任保険」です。借家人賠償責任保険は、一般的に単体での契約ができないため火災保険(家財保険)とあわせて加入します。賃借人用の火災保険には、賠償責任保険の補償が含まれている場合も多いです。賃貸の場合、入居者(賃借人)が原状回復の義務を負っていることから、ストーブを消し忘れて壁の一部が焦げてしまった、蛇口の締め忘れで床が水浸しになり床に損害が発生したといった場合、修繕にかかる費用を入居者(賃借人)が負担することになります。壁や床などの修繕にかかる費用は高額になるケースも多いため、借家人賠償責任保険に加入することで、予期せぬアクシデントによって発生してしまう経済的なリスクに備えることができます。
近隣住民への賠償補償
賃貸物件の場合、水漏れなど自室のトラブルによって他人の部屋の家財に損害を与えてしまった場合にも、高額な損害賠償責任を負ってしまうケースがあります。そんな日常生活における賠償事故に備える補償が「個人賠償責任補償」です。他にも日常生活の事故によって他人にケガをさせたり、ものを壊してしまったりした場合などでも、過失だと認められれば補償が受けられます。契約する火災保険やプランによって補償の上限額が異なりますが、多くは1億円などの高額補償になっています。
賃貸物件の火災保険加入事情
賃貸契約を結ぶ際、不動産会社や貸主から火災保険への加入を求められるのが一般的です。ほとんどの賃貸契約書には、火災保険に加入する義務が明記されており、加入しないと契約が成立しない場合もあります。そのため、不動産会社から勧められた保険に加入するケースが多いですが、自分で好きな保険会社の商品を選んで契約することもできます。自分で保険を選べば、保険料が節約になるケースもありますので、数社の火災保険を比較検討して、賃貸の契約時、あるいは更新時に「自分で加入する旨」を不動産会社に伝えましょう。
賃貸物件で火災保険に加入する理由
火災保険に加入することには、いくつかの重要な理由があります。
原状回復義務の重要性
賃貸物件では、退去時に「原状回復義務」があります。つまり、借りていた部屋に経年劣化以上の損害を与えた場合、その修理費用を負担しなければならないことがあります。ただし、退去時にかかる一般的な修理費用は、火災保険の支払い対象にはなりません。
退去時ではない時に、火災や水漏れなどで建物に損害を与えてしまった場合、借家人賠償責任保険がその費用を補償してくれます。なお、こちらは通常の生活による汚損や時間経過による変化などは含みません。
賃貸物件における火災保険の選び方
- 補償内容:
自分の生活スタイルや住まいの周辺環境に適した補償内容を選びましょう。居室に家財が多い場合は、家財保険の保険金額が不足しないように設定しましょう。 - 特約の追加:
契約前に自分に必要な補償内容を確認し、必要な特約(個人賠償責任補償など)を追加する。 - 補償額の見直し:
必要以上に高い補償額にしないように注意し、実際に必要な金額を設定しましょう。 - 保険期間や支払い方法の工夫:
一括払いにするのが一般的で、保険料面でも有利になります。
転居時の火災保険の手続き
引っ越しをする場合、火災保険は住所変更の手続きが必要になるだけではなく、解約の手続きが必要になることがあります。
契約している家財の火災保険を続ける場合・・・転居先でも補償を受けられるよう、住所変更などの手続きが必要になります。所在地や建物構造等が変わる場合は、保険料の追加や返還が生じる場合があります。
転居を機に契約している火災保険を解約して、転居先で新たに家財の火災保険に加入する場合・・・火災保険を途中で解約すると、残りの保険期間に応じて保険料の一部が解約返戻金として戻ってくることがあります。残りの保険期間が短くなるほど解約返戻も少なくなるので、転居時期にあわせて速やかに手続きしましょう。
賃貸物件では、賃貸借契約時に契約した火災保険は、退去と同時に解約するよう管理会社から求められるのが一般的です。引っ越し先も賃貸物件の場合は、新たな転居先で火災保険の契約が必要になります。
また、転居先が浸水や土砂災害などのリスクの高い場所であれば、水災補償は欠かせません。ハザードマップを活用し、補償内容も見直す必要があるか否かをよく確認しましょう。居住地によって、リスクが異なることもありますので、火災保険は補償内容をよく理解し、自分の生活環境に合ったプランを選ぶことが重要です。
ファイナンシャルプランナーによるコメント
賃貸物件の契約をおこなう際や更新時には、賃借人用の火災保険への加入を促されるのが一般的です。賃貸物件で一人暮らしの場合、保険料の相場は年間4,000~6,000円程度で、更新期間が2年であれば、2年分をまとめて支払うケースが多くなっています。
家財保険の保険金額は300万円程度が一般的です。保険料は補償内容や契約年数、家族構成や世帯主の年齢、加入する商品などが影響して決定します。また、年齢が高くなるほど所有する家財が多い傾向にあるため、十分な補償を得るためには保険金額も高く設定する必要があり、保険料も高くなりがちです。不動産会社から勧められた火災保険に加入する方が多くなっていますが、自分で好きな会社の保険を選ぶことも可能です。近年では、賃借人用の火災保険を扱う保険会社が増えていますので、勧められたものにそのままサインするのではなく、自分で調べて、リーズナブルな保険を探してみてはいかがでしょうか。

| 監修者 | 畠中 雅子 (はたなか まさこ) |
|---|---|
| Webサイト | ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ |
| SNS | |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。 |
どの保険会社がいいのか悩んでいる方は、ぜひ火災保険瞬間比較見積もりをお試しください。
瞬間見積もりは、3つの質問に回答するだけで火災保険の複数社の保険料をすぐに確認することが可能です。
また、火災保険のおすすめ人気ランキングも公開しております。
よく見られているおすすめコラム
保険の基礎知識

地震保険の必要性
日本は世界的にも「地震国」と言われています。
地震はひとたび発生すると、広い範囲に巨大な損害をもたらします。地震による建物の火災や損壊などについては、その発生の予測が困難なことから基本的に火災保険では補償の対象としていません。
続きを見る

水災補償の必要性
近年、突然の集中豪雨や河川の氾濫による建物浸水、土砂崩れによる建物の流失の被害が増加しています。水災補償を付帯すると上記のような災害によって建物や家財に被害があった場合に補償します。
続きを見る
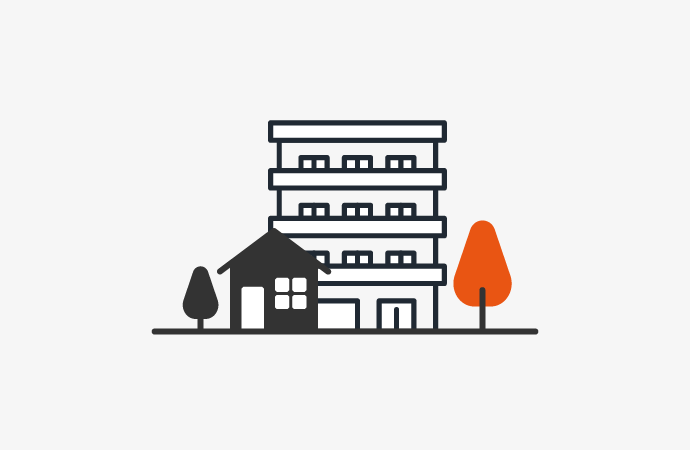
火災保険の必要性
家を保有している以上、万が一に備えて火災保険には加入しておく必要があります。ここでは、火災保険に入っておくべき理由を解説していきます。
続きを見る