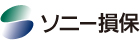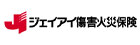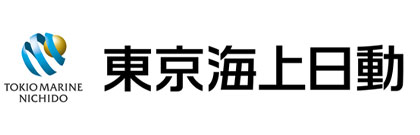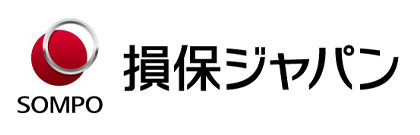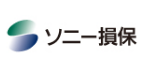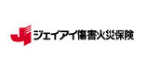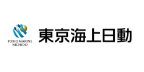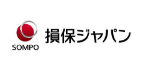火災保険の基礎知識
火災保険と年末調整:控除を受けるためのすべて
年末調整や確定申告の時期になると、多くの人が控除を受けるために必要な手続きを行います。そこで、火災保険の控除について気になる方も多いことでしょう。この記事では、火災保険が控除を受けられるのかについて詳しく解説します。

火災保険は年末調整で控除を受けられるのか?
火災保険は、残念ながら年末調整や確定申告で控除を受けることはできません。所得税や住民税の控除対象となる保険ではないため、税金の軽減にはつながりません。
旧長期損害保険の経過措置について
2006年末までに契約した旧長期損害保険に関しては、経過措置として一定の条件下で税法上の控除対象とされるものがありました。しかし、これも2010年4月1日以降に開始する契約からは廃止され、経過措置も適用されないため、現行の税制では火災保険は控除の対象からは外されています。
地震保険は年末調整で控除を受けられる
一方、地震保険は年末調整や確定申告において、地震保険料控除を受けることができます。地震保険料は、税法上で認められた控除対象となっており、控除を受けることで所得税や住民税を軽減できます。地震保険に加入している場合は、年末調整や確定申告の際に控除額を申告しましょう。
地震保険の控除対象と限度額
地震保険料控除は、1年間に支払った地震保険の保険料に対して適用されます。5年分をまとめて支払っていたとしても、控除の対象になるのは、当該の1年分だけです。また、控除の対象となる金額には限度がありますので下記図をご覧ください。
経過措置が適用される長期損害保険料

(注1)1つの契約で地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、納税者の選択によりいずれか一方の控除を受けることとなります。
(注2)複数のご契約を通じ、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料を合算する場合の限度額は、所得税が50,000円、住民税25,000円となります。
地震保険料控除証明書の取得方法
地震保険に加入している場合、保険会社から年末調整に必要な「地震保険料控除証明書」が送付されます。この証明書は、地震保険料控除を受けるために必要な書類であり、年末調整時に勤め先の会社に提出したり、確定申告の際に使用します。近年では、保険会社によって電子発行に対応しているところも出てきています。電子発行に対応していれば、インターネット経由で簡単に取得できるため便利です。
年末調整での手続き方法
年末調整の際、地震保険料控除を受けるためには、控除証明書を勤務先に提出する必要があります。証明書が手元に届いたら、他の年末調整用の書類とともに勤務先に提出することで所得税や住民税の軽減を受けられます。
確定申告での申請方法
年末調整には間に合わなかったなどで地震保険料控除を受けられなかった場合や、個人事業主などは確定申告の際に地震保険料控除の申告できます。確定申告では、申告書に控除証明書を添付し、支払った地震保険料を記入します。確定申告の基本は納税のための申告になりますが、源泉徴収されている税金がある場合は、控除額が増えることで税金が還付されるケースもあります。
ファイナンシャルプランナーによるコメント
火災保険は控除の対象外ですが、地震保険は控除対象となり、年末調整や確定申告で地震保険料控除を受けることができます。地震保険に加入している場合、毎年送付される控除証明書に記載された金額を年末調整用の書類に記入したり、確定申告書に記入して、税制上のメリットを活用しましょう。

| 監修者 | 畠中 雅子 (はたなか まさこ) |
|---|---|
| Webサイト | ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ |
| SNS | |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。 |
どの保険会社がいいのか悩んでいる方は、ぜひ火災保険瞬間比較見積もりをお試しください。
瞬間見積もりは、3つの質問に回答するだけで火災保険の複数社の保険料をすぐに確認することが可能です。
また、火災保険のおすすめ人気ランキングも公開しております。
よく見られているおすすめコラム
保険の基礎知識

地震保険の必要性
日本は世界的にも「地震国」と言われています。
地震はひとたび発生すると、広い範囲に巨大な損害をもたらします。地震による建物の火災や損壊などについては、その発生の予測が困難なことから基本的に火災保険では補償の対象としていません。
続きを見る

水災補償の必要性
近年、突然の集中豪雨や河川の氾濫による建物浸水、土砂崩れによる建物の流失の被害が増加しています。水災補償を付帯すると上記のような災害によって建物や家財に被害があった場合に補償します。
続きを見る
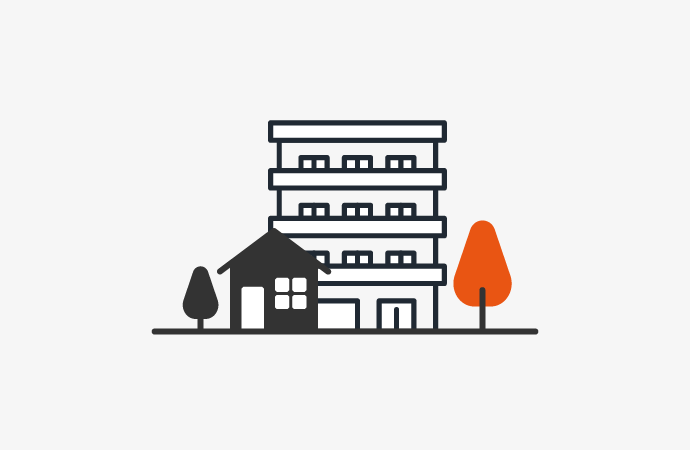
火災保険の必要性
家を保有している以上、万が一に備えて火災保険には加入しておく必要があります。ここでは、火災保険に入っておくべき理由を解説していきます。
続きを見る