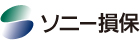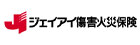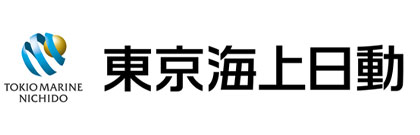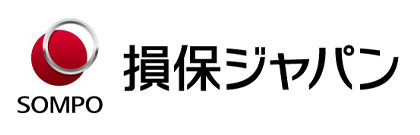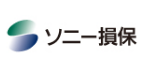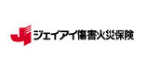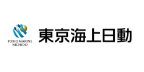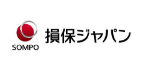火災保険の基礎知識
火災保険と地震保険の違い:必要性と補償内容を解説
火災保険と地震保険は、どちらも住宅に関わる重要な保険ですが、補償内容や補償対象に大きな違いがあります。本記事では、火災保険と地震保険の違いについて詳しく解説し、それぞれの特徴や加入方法を紹介します。

火災保険とは
火災保険の補償内容は非常に広範囲で、主に以下のリスクをカバーします。
火災保険の詳細はこちらをご覧ください。
地震保険とは
地震保険は、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じる損害に備えるための保険です。
被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、対象が「住居として用いられる建物(建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいるもの)及び「家財」に限られます。
また、「家財」については生活用動産に限られ、貴金属、宝石、書画など、1個または1組の価額が30万円を超えるものや現金、預貯金証書、切手、印紙などについては保険の対象に含まれません。
地震保険の補償内容
地震保険の補償内容は、主に以下の点が含まれます。
- 建物:地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災や住宅の倒壊や損壊
- 家財:地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災や家財の損壊
地震保険は、火災保険では補償対象外となる地震や噴火、またはこれらを原因とする津波によって生じた損害や、地震が原因となる火災による損害が補償の対象です。
地震保険で支払われる金額の目安
地震保険で支払われる保険金は、実際にかかった修理費用ではなく、対象となる建物や家財の損害の程度に応じて、以下の4段階のいずれかの割合の保険金が支払われます。
- 全損:地震保険金額の100%
- 大半損:地震保険金額の60%
- 小半損:地震保険金額の30%
- 一部損:地震保険金額の5%
※ ただし、損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険の加入方法
地震保険は、単体では加入ができません。そのため火災保険とセットで加入する必要があります。すでに火災保険に加入しているものの、地震保険には未加入の場合は、保険期間の途中でも地震保険に追加で加入することが可能です。
火災保険と地震保険の違い
① 補償内容
火災保険は、火災や落雷、水災や盗難などによる損害を補償するのに対し、地震保険は火災保険では補償の対象外となる地震や噴火、またはこれらによる津波や火災を原因とする建物や家財の損害を補償します
② 保険料
地震保険料は、保険の対象である「居住用建物および家財を収容する建物の所在地」と「建物の構造」を基準に、「建物の免震・耐震性能による割引」を加味して決まります。地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき補償内容や保険料が決まっているため、どの保険会社で加入しても内容に違いはありません。
③ 所得控除の対象かどうか
火災保険は所得税や住民税の控除対象にはなりませんが、地震保険は一定の条件を満たすことで地震保険料控除を受けることができます。地震保険料控除とは、1年間の払込保険料に応じて一定の額を所得金額から控除できる制度で、地震保険料控除を適用することで課税所得が減り、その結果、所得税や住民税の負担を軽減できます。
詳しくは「火災保険と年末調整:控除を受けるためのすべて」をご覧ください。
④ 支払われる保険金の違い
地震保険の保険金額はセットで契約する火災保険の保険金額とは別に定めることになっており、火災保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で設定します。
- 建物:火災保険の保険金額の30%~50%(ただし5,000万円を限度)
- 家財:火災保険の保険金額の30%~50%(ただし1,000万円を限度)
※ 保険会社によっては、独自の上乗せ補償を扱う会社もあります。
地震保険に入る必要性
火災保険では地震や噴火、これらによる津波が原因の損害は補償されません。地震等が原因で生じた建物や家財の損害は、地震保険を付帯していないと補償されず、しかも建物の損壊が大きい場合は、建て直しにかかる費用も高額になるのが一般的なので、マイホームを持っている方にとって、地震保険に入るのは大切なことだといえるでしょう。
公的支援の限界
大規模な地震が発生した場合には、罹災証明を取ることで政府や自治体から公的支援が行われるのが一般的です。公的支援はもちろん有難い制度ですが、公的支援だけで、家の建て替え費用をまかなうのは無理があります。地震保険にも建物は5,000万円、家財は1,000万円と支払限度額が設定されていますが、生活再建をはかるためには地震保険からの保険金は欠かせない存在になるでしょう。
どんな人に地震保険が必要か
発生頻度については地域によって差があるものの、どこに住んでいても地震のリスクからは逃れないのが日本です。そのため、地震の発生確率に関わらず、地震保険には加入しておくのが安心です。特に、マイホームの取得から日が浅く、住宅ローンがたくさん残っている場合などは、地震保険からの保険金が受け取れないと、住宅再建が難しくなってしまう可能性がありますので、火災保険には地震保険を付帯するようにしましょう。
地震保険の注意点
補償対象外となるケース
地震保険には補償対象外となるケースもあります。例えば、家の一部と思われても、門・塀・垣のみに生じた損害や、地震の程度が一部損に至らない損害、地震と無関係な経年劣化や施工不良などによる損害などは対象外となります。
地震保険の割引制度
地震保険にも一定の条件を満たすと保険料が安くなる「割引制度」があります。主に建物の耐震や免振性能に応じた割引や建築年による割引が用意されており、割引制度を活用することで、保険料を抑えることができます。詳細は下記をご覧ください。
建物の性能による保険料の割引率
| 割引の種類 | 割引の条件 | 保険料の割引率 | |
|---|---|---|---|
| 免震建築物割引 | 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 | 50% | |
| 耐震等級割引 | 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | 耐震等級3 | 50% |
| 耐震等級2 | 30% | ||
| 耐震等級1 | 10% | ||
| 耐震診断割引 | 対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | 10% | |
| 建築年割引 | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% | |
ファイナンシャルプランナーによるコメント
小規模なものまで含めれば、日本のいたるところで地震は頻発しています。日本の地形を考えれば、地震の発生は避けられない現実があります。
そんな日本においては、地震の発生に備える必要があります。家屋の再建費用などを捻出するために加入するのは地震保険です。
万が一、大規模地震が発生して、家屋が倒壊するなどの被害が発生した時に、家屋の再建費用などが受け取れるのは地震保険しかないからです。地震が原因で火災が発生した場合でも、地震保険に加入していないと、保険金の支払事由には該当しません。
ちなみに、地震保険は政府と民間保険会社が共同で運営しています。大地震が起こった時、民間の保険会社だけで保険金の支払いができない可能性があるため、政府が再保険を引き受ける形で、保険金の支払いをバックアップしているのです。
そのような背景があるため、地震保険の基本補償はどの保険会社で加入してもほぼ同じです。ただし、地震保険は火災保険とセットでないと契約ができないため、どこの保険会社の火災保険に加入して、その保険に地震保険を付帯するかを考えることになります。

| 監修者 | 畠中 雅子 (はたなか まさこ) |
|---|---|
| Webサイト | ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ |
| SNS | |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。 |
どの保険会社がいいのか悩んでいる方は、ぜひ火災保険瞬間比較見積もりをお試しください。
瞬間見積もりは、3つの質問に回答するだけで火災保険の複数社の保険料をすぐに確認することが可能です。
また、火災保険のおすすめ人気ランキングも公開しております。
よく見られているおすすめコラム
保険の基礎知識

地震保険の必要性
日本は世界的にも「地震国」と言われています。
地震はひとたび発生すると、広い範囲に巨大な損害をもたらします。地震による建物の火災や損壊などについては、その発生の予測が困難なことから基本的に火災保険では補償の対象としていません。
続きを見る

水災補償の必要性
近年、突然の集中豪雨や河川の氾濫による建物浸水、土砂崩れによる建物の流失の被害が増加しています。水災補償を付帯すると上記のような災害によって建物や家財に被害があった場合に補償します。
続きを見る
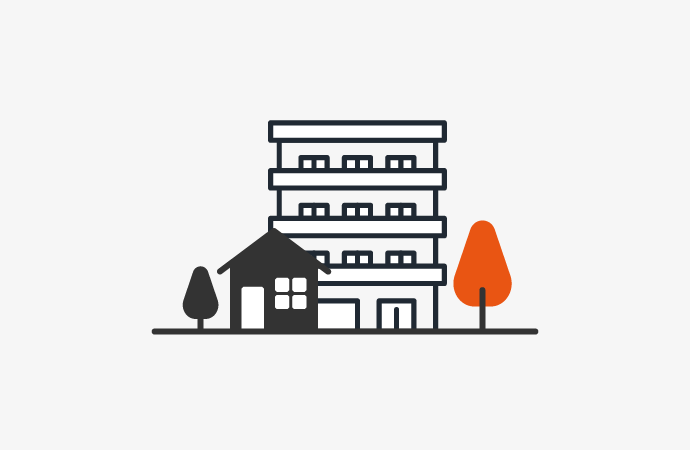
火災保険の必要性
家を保有している以上、万が一に備えて火災保険には加入しておく必要があります。ここでは、火災保険に入っておくべき理由を解説していきます。
続きを見る