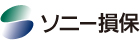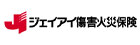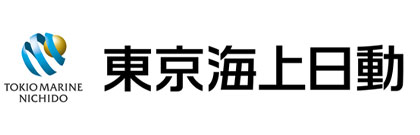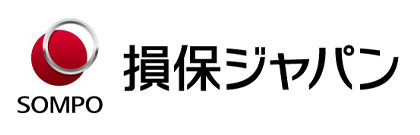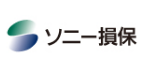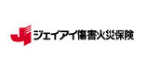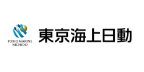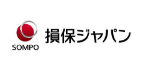火災保険の基礎知識
火災保険の水災補償とは?必要性や補償範囲、請求方法を徹底解説
日本は毎年、何度も台風が通過していますし、近年では線状降水帯の影響による局地的な豪雨も発生しています。豪雨の影響で河川が決壊し、洪水が発生するといった水災(水害)のリスクも高くなっています。大規模洪水や河川の氾濫などの様子をメディアを通して見る機会が増えていますが、その被害の状況は、拡大しているともいえます。そのような地形的リスクを持つ国に住んでいる以上、住まいを守る保険として「火災保険の水災補償」の役割はより重要になっています。そこで本記事では、水災の定義から補償範囲、請求方法までをわかりやすく解説します。

水災(水害)とは?
水災とは、大雨や台風、洪水、高潮などの自然災害により発生する浸水・冠水・土砂流入などの被害を指します。特に近年は気候変動の影響により、局地的な大雨(ゲリラ豪雨)による被害が増加しています。
火災保険の水災補償とは
火災保険における水災補償とは、建物や家財が水災によって損害を受けた場合に、その被害の度合いに応じた損害額を補償する制度です。もともと水災補償は、「特約」として選択できる仕組みでしたが、昨今の水災の頻度の高まりや、ニーズの高さから基本補償に組み込まれる商品が多くなっています。
水災補償の必要性
浸水による被害は、床上・床下浸水にとどまらず、建物の構造自体に深刻なダメージを与えることもあります。水につかってしまうと、家財の損傷は大きく、水が引いたからと言って、それ以前と同じように使用できるわけではありません。特に長時間水につかると腐りやすい木造住宅や、低地に建つ住宅では水害による損害リスクは高く、修繕費用も高額になるため、水災補償の必要性は非常に高いといえます。
水災によって自宅が損害を負った場合の制度
水災によって住宅や家財が損害を受けた場合、火災保険の水災補償によって再建費用や修理費用が支払われます。補償金額は、被害状況や加入している保険の内容によって異なります。床上浸水についても、浸水の深さが「地盤面より45センチ以上」などの条件が支払い要件となる場合もあります。
水災と間違えやすい被害
以下のような被害は、水災と混同されやすいですが、補償の対象外となることがあります。
地震による津波・土砂崩れ
地震が原因で発生した津波や土砂崩れによる被害は、水災ではなく地震保険の補償対象です。
水濡れ、漏水
給排水管の破損や設備不良による漏水は、水災補償ではなく「水濡れ補償」の対象となります。
風・雹(ひょう)・雪
台風による強風や雹、雪による損害も「風災」「雪災」として別枠の補償が設定されている場合があります。
水災補償を受けられる条件
水災補償を受けるには、以下のような条件を満たしている必要があります。
特約が付帯されていた場合の保険金額
火災保険の基本契約に水災補償が組み込まれているか、水災補償特約が付帯されていないと補償対象外となります。また、家財に対する補償も別契約である場合があるため、契約時に詳細を確認しておくことが重要です。
水災で自動車が水没した場合
洪水での冠水などが原因で所有する車が水没してしまった場合はどうなるでしょうか。「家財保険に加入していたら補償されるのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。しかし、残念ながら火災保険や家財保険では自動車は補償の対象外です。
では、水害によって、車が損害を受けた場合に補償を受けるにはどうしたらよいでしょうか。正解は自動車保険に車両保険を付帯することです。車両保険を付帯していれば、一般タイプでもエコノミー(限定)タイプでも補償の対象となります。
ファイナンシャルプランナーによるコメント
火災保険の水災補償は、思わぬ自然災害から大切な住まいと財産を守る心強い備えです。自宅の近くに河川があったり、台風の通り道になりやすい場所など、水災のリスクがある地域に住んでいる場合は特に必要性が高く、補償範囲や契約内容を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。いざという時に適切に請求手続きを行えるよう、水災補償の範囲についての理解を深めておきましょう。

| 監修者 | 畠中 雅子 (はたなか まさこ) |
|---|---|
| Webサイト | ファイナンシャルプランナー 畠中雅子のミニチュアワールド見学ブログ+観光列車乗車ブログ |
| SNS | |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学時代にフリーライター活動をはじめ、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、数多くのメディアへの寄稿や監修業務。セミナー、相談業務などを行う。メディアへの掲載、登場回数は1万回を超えている。著書は「70歳からの人生を豊かにするお金の新常識」(高橋書店)ほか、70冊を超える。大学院在学中にソルベンシーマージンに関する論文を執筆したことから、保険分野の仕事も数多く手がけている。 |
どの保険会社がいいのか悩んでいる方は、ぜひ火災保険瞬間比較見積もりをお試しください。
瞬間見積もりは、3つの質問に回答するだけで火災保険の複数社の保険料をすぐに確認することが可能です。
また、火災保険のおすすめ人気ランキングも公開しております。
よく見られているおすすめコラム
保険の基礎知識

地震保険の必要性
日本は世界的にも「地震国」と言われています。
地震はひとたび発生すると、広い範囲に巨大な損害をもたらします。地震による建物の火災や損壊などについては、その発生の予測が困難なことから基本的に火災保険では補償の対象としていません。
続きを見る

水災補償の必要性
近年、突然の集中豪雨や河川の氾濫による建物浸水、土砂崩れによる建物の流失の被害が増加しています。水災補償を付帯すると上記のような災害によって建物や家財に被害があった場合に補償します。
続きを見る
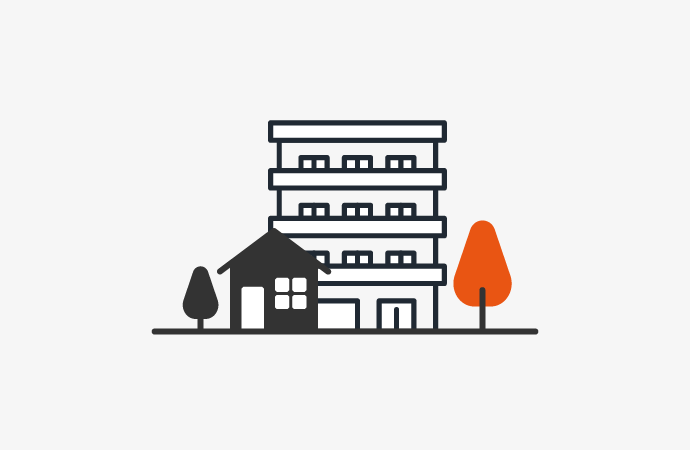
火災保険の必要性
家を保有している以上、万が一に備えて火災保険には加入しておく必要があります。ここでは、火災保険に入っておくべき理由を解説していきます。
続きを見る