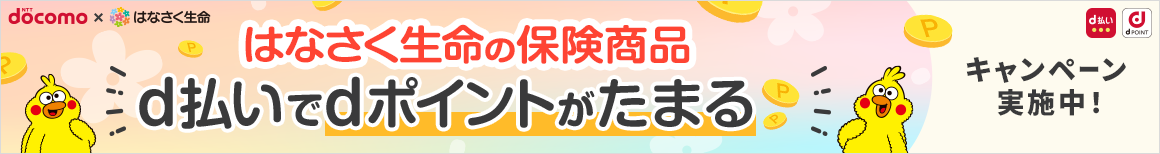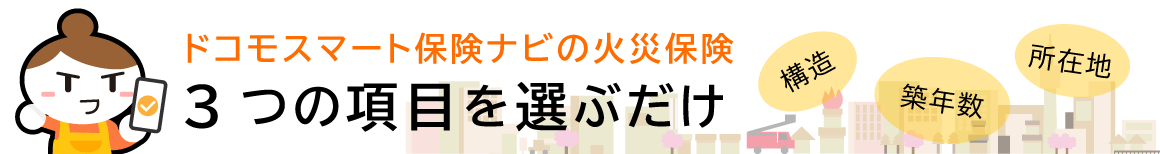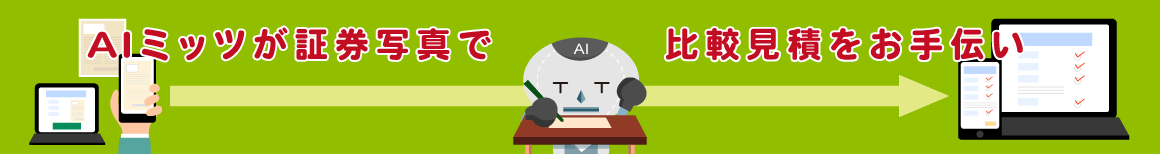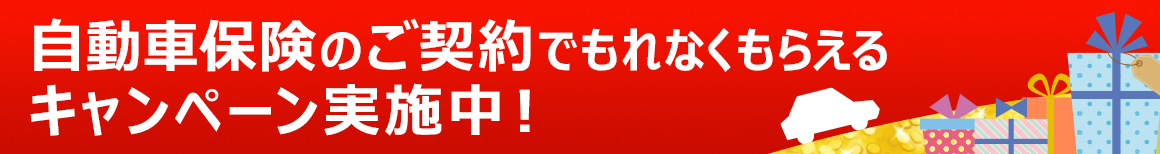保険の基礎知識
収入保障保険を検討していますが、保険期間は何歳までがオススメでしょうか?

伊藤 拓哉さん(仮名 35歳 Webデザイナー)のご相談
私に万が一のことがあった場合に備えるために、生命保険への加入を検討しています。収入保障保険に加入するのがよいと思うのですが、保険期間は何歳までとするのがよいでしょうか? 最適な年齢を教えてください。
伊藤 拓哉さん(仮名)のプロフィール
| 家族構成 | |||
|---|---|---|---|
| ご相談者 | 伊藤 拓哉 さん | 35歳(Webデザイナー) | 手取り年収 470万円 |
| 配偶者 | 30歳 | ||
| 長女 | 5歳 | ||
| 長男 | 3歳 | ||
| 貯蓄額 | 300万円 |
|---|

村井 英一
(むらい えいいち)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- ご家族の状況によって、最適な保険期間は異なります
- ご主人さまと奥さまの働き方、お二人の年齢差などが検討のポイントになります
- 支払保証期間は短くてもよいでしょう
お子さまが自立した後の生活費の補てんが必要かどうかで違ってきます
1.保険期間が長いほど、保険料は高くなります
一般の定期保険は、保険期間中に亡くなった場合は事前に決めてある保険金額を受け取れます。それに対して収入保障保険は、一度にまとまった保険金が出るのではなく、「毎月10万円」といった年金を、あらかじめ定めた年齢まで継続して受け取れる仕組みになっています。「あらかじめ定めた年齢」とは、保険加入時に選択した保険期間の年齢です。被保険者はすでに亡くなっているのですが、「生きていればなるはずであった年齢」まで年金を受け取れます。保険商品によって異なりますが、40歳から90歳ぐらいまでの間で選択することができます。
亡くなった場合、そのときから保険期間の年齢まで毎月年金が出ますので、受け取る年金の総額は、亡くなった年齢と保険期間の年齢によって変わります。保険期間の年齢が高いほど年金を受け取る期間が長く、つまり多くの年金を受け取ることになります。その分、保険料は高くなります。例えば、35歳男性が年金月額10万円で加入した場合の保険料を、ある保険会社で比べてみました。すると、保険期間を55歳にした場合に比べて、60歳にすると約20%、65歳にすると約50%上昇します。
保障は充実させたいが、保険料は安い方がよい。相反するメリットの間で、ご家族の状況を踏まえて、最適解を選ぶことが大切です。それにはまず、保険に加入する目的を今一度確認しましょう。
2.最適な保険期間はご家族の状況で
多くの人にとって収入保障保険に加入する目的は、ご家族の生活保障ではないでしょうか。一家の大黒柱であるご主人さまが亡くなられた後も、奥さまとお子さまが生活していけるように、との備えです。しかし保障の必要性を、さらに詳細に考えてみます。
中心は、お子さまが自立できるまでの生活費と学費の手当てでしょう。もし、この部分だけをカバーできれば十分なのであれば、下のお子さま(末子)が大学を卒業する時のご自身の年齢まで加入すればよいでしょう。万が一の場合は、収入保障保険からの年金で、下のお子さまが自立するまで生活費や学費を補うことができます。保障はそこまででよいのです。
一方、お子さまが自立した後の奥さまの生活費も確保しておきたいのなら、保険期間をもう少し長くしておきたいものです。奥さまが65歳になってご自身の年金を受け取れるようになるまで、収入保障保険の年金で生活費の補てんができれば安心です。その分、保険料は高くなりますので、お子さまが自立した後の奥さまの生活費の確保が必要かどうかを確認しておくとよいでしょう。目安となるのは、お二人の働き方です。
①奥さまが働いているか、専業主婦か? 働いている場合はパートか、正社員か?
奥さまの働き方でその後の保障の必要性が異なります。奥さまが正社員で、定年まで安定した収入を見込めるというのであれば、お子さまが自立した後の保障の必要性は低いでしょう。一方、専業主婦や扶養の範囲内でのパート勤務という場合は、お子さまが自立した後も保障が続くと安心です。
②ご主人さまはお勤めか、自営業か?
お勤めの人が死亡した場合、奥さまには遺族基礎年金と遺族厚生年金が給付されます。下のお子さまが高校を卒業したら遺族基礎年金の給付は終了しますが、厚生年金から中高齢寡婦加算というものが給付され、比較的充実した年金を受け取れます。その分、自ら備える保障は小さくても大丈夫です。一方、自営業者の場合、遺族に給付されるのは遺族基礎年金だけです。下のお子さまが高校を卒業したら給付は終了します。奥さまが60歳になると寡婦年金というものが給付されますが、それまでは国からの年金はありません。それだけに、その間の奥さまの生活費を踏まえた保障を確保しておきたいものです。
③ご夫婦の年齢差
ご夫婦の年齢差も検討の要素となります。奥さまが65歳になるとご自身の年金が給付されますが、それまでの生活費をどのように賄うのかを考えておく必要があります。必ずしも、奥さまの65歳までの保障を確保しなければならないというわけではありません。しかし年齢が離れていれば、保険期間を長くしておかないと、奥さまが65歳になるまでの空白期間が長くなってしまいます。
これらの要素を考慮しながら、保険期間を検討するとよいでしょう。ご自身の定年退職の年齢に合わせて保険期間を決める人も少なくありません。収入保障保険の年金を、亡くなったご主人からの〝お給料〟に例えられることが多いからでしょうか。気持ちとしてはわからないでもありませんが、それよりもご遺族の状況に合わせることの方が大切です。ご主人さまの定年年齢にはこだわらず、ご遺族の収入の見通しを考慮して検討するのがよいでしょう。
3.支払保証期間も決める必要があります
収入保障保険は、保険期間の年齢で年金の支払いが終了します。例えば、60歳で設定していると、59歳で亡くなった場合は1年間しか年金を受け取れないことになります。そこで「支払保証期間」というものを設定して、年金を受け取れる最低限の年数を定めている商品が多くあります。支払保証期間を3年と設定しておくと、59歳で亡くなっても3年間は年金を受け取れます。年金額が月額10万円であれば、最低でも360万円は保証されるわけです。受け取れる期間とともに最低金額も確保していることになります。保険会社によって扱いは異なりますが、1年から5年程度を選択できるケースが多くなっています。長い方が安心ですが、この点も保険料に反映されます。保証期間が短い、あるいは設定しない方が毎月の保険料は安くなります。
この制度は、「毎月ずっと保険料を払ってきたのに、ほんの少ししかもらえなかった」という事態を回避するための仕組みです。しかし、そもそも収入保障保険は保険金額が徐々に低下していく保険です。その分、一般の定期保険に比べて保険料が安くなっています。そして、残りの保険期間が短いということは、ご家族にとっての必要な保障額が小さいということでもあります。保険期間の最後は、必要な保障額はかなり小さいはずで、受け取れる年金額が小さくなるのは、ご家族の状況に合っているといえます。商品の仕組みを理解していれば、支払保証期間はなるべく短く、あるいはなくてもよいでしょう。
収入保障保険の保険期間は何歳までが正しいかとのご質問をいただきました。ご家族の状況によって異なりますので、「〇歳が正しい」とは一概に言えません。上記に挙げた、3つの要素を考慮しながらご検討されてください。そして、保険料の金額を踏まえながら、ご家族にとっての最適解を見つけられてください。

| 執筆者 | 村井 英一 (むらい えいいち) |
|---|---|
| Webサイト | https://kakeinoshindan.com/ |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大手証券会社で長年、資産運用の相談を受けた。ファイナンシャル・プランナーとして独立後は、家計診断、保険の選択、住宅ローンなどで、多くのお客様からのご相談を受ける。シミュレーション分析を得意としており、20年後、30年後の家計の状況を推測して提案を行う。また、全国各地で家計管理に関する講演を行っている。 |