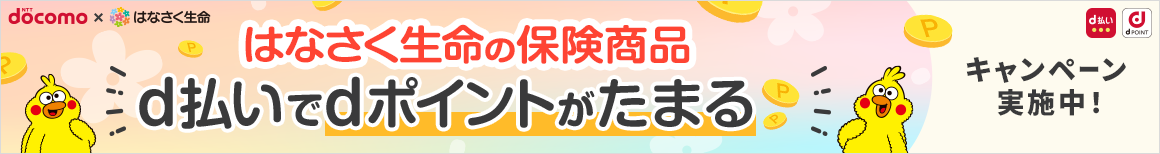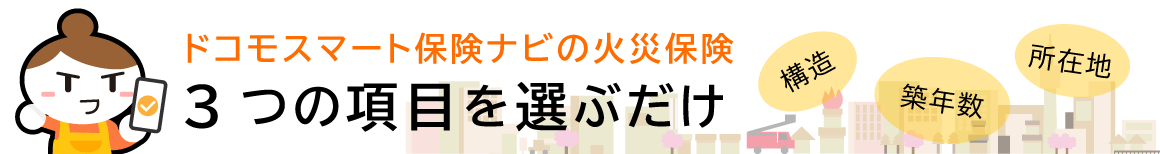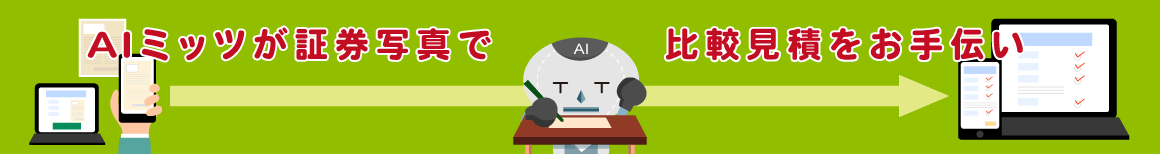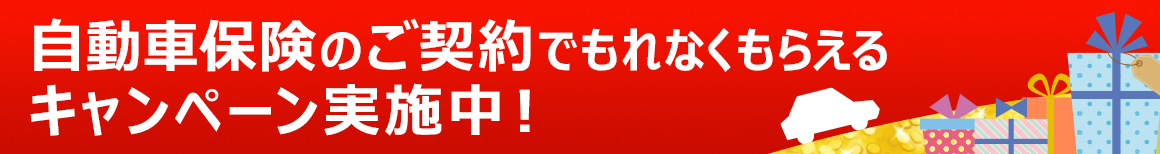保険の基礎知識
健康保険と生命保険の違いがわかりません。会社員が強制加入する保険を教えてください。

早瀬 菜緒さん(仮名 22歳)のご相談
この春に新社会人になりました。これからは少しずつでも、貯蓄や保険をはじめとする生活設計を考えていきたいと思っています。ですが、これまで加入経験もなく、殆ど気にしてこなかったので、生命保険と会社の健康保険との違いがよくわかりません。強制加入で保険料が給与天引きされる保険がいくつかあると聞きましたが整理しきれていません。
社会人として意識を高めるためにも、会社員がどのような保険に加入するのか教えてください。
早瀬 菜緒さん(仮名)のプロフィール
| 家族構成 | 年齢 | 職業 | 居住 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 22歳 | 会社員 | 同居 |
| 父親 | 52歳 | 会社員 | |
| 母親 | 50歳 | 会社員 | |
| 妹 | 17歳 | 学生 |

井上 信一
(いのうえ しんいち)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- 社会保険は全部で5つあり、会社員はその全てに加入します
- 原則、社会保険の保険料は、収入に応じて負担しますが、万一の際に手厚い給付を受けられます
- 皆保険である公的医療保険として、会社員が加入するのが「健康保険」です
強制加入となるのが健康保険などの社会保険です。
保障(補償)される範囲が幅広く、様々な給付を受けられる社会保険を理解することが大切です。
早瀬さま、新社会人のスタートおめでとうございます。また、ご相談ありがとうございます。
ご相談にある保険とは、社会保険(社会保険制度)のことですね。健康保険を中心に、社会保険の保障(補償)の概要をご理解いただこうと思います。
社会保険は全部で5つ、会社員等はその5つすべてに加入します
原則として強制加入で、国が国民のために保障(補償)している制度を社会保険といいます。
一方、社会保険に対し、個人が任意で加入する生命保険や損害保険等を私的(民間)保険と呼ぶこともあります。
社会保険は、国民が経済的に困窮しないよう生活の安定を図るためにある制度で、加入者(被保険者)は収入の一定割合等を保険料として負担する代わりに、受給要件を満たした際には各種の給付を受けられます。
具体的には、医療、年金、介護、失業、労働災害に関して、以下の5つの社会保険に分けられています。
| 社会保険の種類 | カテゴリー | 保障(補償)の給付内容の概要 |
|---|---|---|
| ①公的医療保険 | 医療 | 業務外の事由での病気・ケガ、休業、出産等に対する給付 |
| ②公的年金保険 | 年金 | 老齢・障害・遺族に対する生活保障(年金等の給付) |
| ③公的介護保険 | 介護 | 要介護状態や要支援状態に対する給付 |
| ④労働者災害補償保険 (労災) |
医療 (労働災害) |
業務上の事由または通勤途中での病気・ケガ、休業、障害等に対する給付 |
| ⑤雇用保険 | 失業等 | 求職者(失業)、雇用促進、雇用継続(育児休業や介護休業等)等に対する給付 |
ただし、国民全員が5つの社会保険のすべてに加入する訳ではありません。社会保険の対象者は働き方や年齢等によって変わります。
例えば、早瀬さまのような会社員等(被用者といいます)は5つすべての社会保険に加入します。ですが、働いていない人はもちろん、個人事業主(会社等に雇われて働く被用者ではない人)は、特段の手続きをしなければ、原則、「④労災」と「⑤雇用保険」のように、雇用されている労働者のための保険の加入対象者とはなりません。
「⑤雇用保険」により、子が生まれた際の育児休業や家族が要介護状態になった際の介護休業の際にも一定の給付を受けられるのは、会社員等の被用者だけが享受できる保障といえますね。
次に、年齢による要件として、「②公的年金保険」では、65歳になると老齢年金の受給が始まる関係等から、加入期間が定められています。公的年金保険には、原則20歳から60歳の国民全員が加入する「基礎年金」と会社員等が加入する「厚生年金保険」とがあり、会社員等の人はこの両方に加入します(厚生年金保険に加入する人は基礎年金の保険料が不要)。このうち厚生年金保険の加入期間は会社員である間(入社時の年齢は問わない)となりますが、原則70歳までと最長加入年齢が定められています。この加入期間と加入期間中の保険料負担に応じて受給できる年金額が変わってくるしくみです。
また、「③公的介護保険」は40歳以上の人が加入対象となります。40歳未満は対象者ではないので、保険料負担はありませんが、若年性疾病や特殊疾病等で要介護・要支援状態になっても保障はありません。
整理すると、「①公的医療保険」だけが、働き方に関係なく、生まれた時から死亡する時まで加入する社会保険ということになります。国民全員が加入することから「皆保険(かいほけん)」とも呼ばれています。
なお、社会保険では、受給要件が重なるケースもありますが、「各社会保険から重複して給付される」場合はどちらかというと少なく、「併給調整される(いずれか一方の社会保険だけが優先されて給付される、または各社会保険間で給付額が減額調整される)」ことが大半です。
例えば会社員等の場合、病気やケガによる治療・休業を要した際の給付は、その要因が業務中や通勤途中であれば「④労災保険」で保障されますが、業務外事由の場合は「①公的医療保険」からの保障と明確に区別されます。ちなみに、「④労災保険」の保障内容は相対的に手厚いのですが、この保険料は全額、会社が負担していて個人負担はありません。これも、会社員等の被用者が享受できる保障(補償)といえます。
整理しましょう。
社会保険は全部で5つあり、会社員等の場合そのすべてに強制加入(「公的介護保険」は40歳以降)することになります。このうち「④労災」を除き、収入に対し一定料率で計算した保険料を、給与天引きの形で毎月少額ずつ負担するわけですが、何か困った際には、各社会保険から保障を受けられるようになっているのです。
「健康保険」は会社員等が加入する「公的医療保険」です
5つある社会保険の中でも、働き方や年齢に関わらず、国民全員が「皆保険」として加入するのが、「公的医療保険」です。この社会保険に加入しているからこそ、その給付により病院の窓口で支払う医療費が、「定価」でなく自己負担割合で計算された少額で済んでいることになります。
もう少し、「公的医療保険」の制度について詳しくみていきましょう。
「公的医療保険」の加入者は、「被保険者」と、被保険者に生計維持されている「被扶養者」とに分けられます。「被扶養者」には保険料負担はありません。
早瀬さまのご家族は同居されていますが、ご両親とも会社員ですので、各々がお勤め先ごとの被保険者となっている筈です。早瀬さまと妹さんは両親のどちらかの被扶養者であったと考えられますが、このたび社会人になったことで親から独立し、ご自身も被保険者となったというわけです。
次に、「公的医療保険」の種類は、会社員等の被用者が加入する「健康保険」と、働いていない人や個人事業主等、その他の人が加入する「国民健康保険」とに分けられます。
少し細かくなりますが、これら「公的医療保険」の運営主体となる保険者は次のとおりです。
| 制度 | 保険者 | 窓口 | 加入対象者 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 全国健康保険協会 (協会けんぽ) |
日本年金機構、協会の各都道府県支部 | 被用者・被扶養者 |
| 健康保険組合 | 健康保険組合 | ||
| 国民健康保険 | 市区町村・都道府県 | 市区町村役場 | 被保険者・その家族 |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合 | 医師等の士業などの被保険者・その家族 |
早瀬さまは会社員なので、「健康保険」の被保険者となります。
「健康保険」を運営する保険者としては、比較的小規模な企業等が都道府県単位の支部に加入する「協会けんぽ」と、単一の企業グループ等で組合を作る場合や同業同種の複数の企業等が集まり組合を作る「健康保険組合」とに分かれます。
「健康保険」では、原則として健康保険料を企業等と被保険者とで折半して負担するのですが、保険者が「健康保険組合」の場合、被保険者の負担割合が低めで、万一の際の給付も独自の上乗せ保障が設定されていることも少なくはありません。
なお、「健康保険」「国民健康保険」の被保険者・被扶養者も、原則として75歳になると、これらとはまた別の、後期高齢者医療広域連合が保険者となる「後期高齢者医療制度」の被保険者に移行します。
まず「健康保険」での保障を理解しましょう
「公的医療保険」の被保険者および被扶養者となることで受けられる保障は多岐にわたります。その代表的なものが『療養の給付』です。具体的に給付金を受けるという「現金給付」ではありませんが、病院等の窓口で支払う医療費用が、以下のように年齢等によって、所定の自己負担割合に応じた額で済む「現物給付」という形で保障を受けられます。
| 対象者 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 被保険者・被扶養者で以下以外 | 3割 |
| 小学校就学前の児童 | 2割 |
| 70歳以上75歳未満 (現役並み所得者を除く) |
2割 |
なお、「公的医療保険」で保障対象となる医療費等は、国によって認められている「保険診療」に限られます。
一般的な治療の殆どは「保険診療」ですが、いわゆる自由診療といわれる医療や先進医療の技術料等については、「公的医療保険」が適用されず全額自己負担となります(例外的扱いとして、別途、国で指定されている先進医療や患者申出療養を受けた場合における「保険診療」の対象となる基礎部分は、「公的医療保険」の保障対象となります)。
その他にも、「公的医療保険」では、1か月間の自己負担額が所定の限度額を超える場合、超える額が現金給付(または現物給付)される『高額療養費』の制度や、入院時の食事やその他の生活療養費を所定額に抑える『入院時食事療養費』や『入院時生活療養費』などがあります。
また、一般的に「国民健康保険」にはなく、「健康保険」だけの給付として、以下のような保障もあります。
傷病手当金(被保険者のみ保障)
病気やケガで就業不能となり給与を受けることができない時に、給与の代わりに、休業前給与等の一定割合を、連続3連休を満たせば4日目の休業日から、通算で最長1年6か月間受け取れる保障
出産手当金(被保険者のみ保障)
出産のために休業し給与を受けることができない時に、給与の代わりに、休業前給与等の一定割合を、一定期間受け取れる保障
今回は社会保険の概要をかいつまんでご説明しましたが、その保障内容は多岐にわたります。病気やケガ等を保障する「公的医療保険」の給付内容も、このほかにも様々なものがあります。会社の福利厚生制度も含め、どういう保障があるのか、ある程度でも把握するには時間がかかるものです。会社員となったことで、幅広く社会保険からの保障が約束されているわけですので、まずは社会保険を理解することが大切です。
生命保険や損害保険または貯蓄等、自助努力での準備が求められるのは、こうした社会保険の保障や勤め先で整備されている独自保障を考えた上で、なお不足する部分の補完といえます。追加で補足していく生命保険等は、ゆっくり、じっくりと探していく姿勢でも悪くはないと思います。

| 執筆者 | 井上 信一 (いのうえ しんいち) |
|---|---|
| Webサイト | https://www.shinichi-inoue.com/ |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学卒業後、大手メーカーでの業務の中でライフプランの必要性を肌で感じFPとなる。以後、FP教育会社、リスクマネジメント会社のFP部門を経て2010年に独立開業。年間約100件の相談、約500時間の講師業のほか、企業の福利厚生相談、執筆・監修等にも従事。「最終的にお客様が選ぶ道は1つでも、FPの付加価値としていかに多角的な発想や選択肢を提案できるか」を信条としている。成年後見人として地域福祉への貢献活動もおこなっている。 |