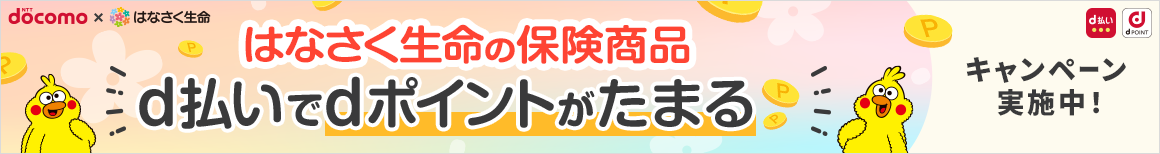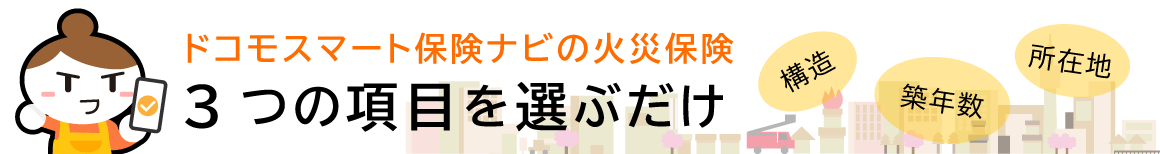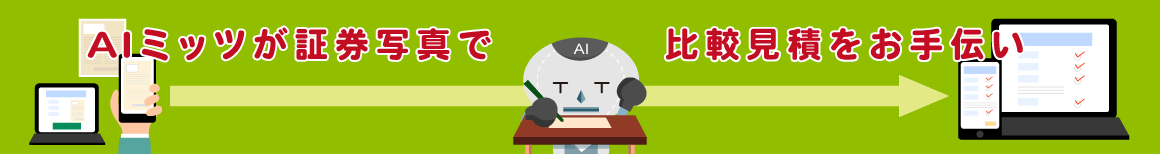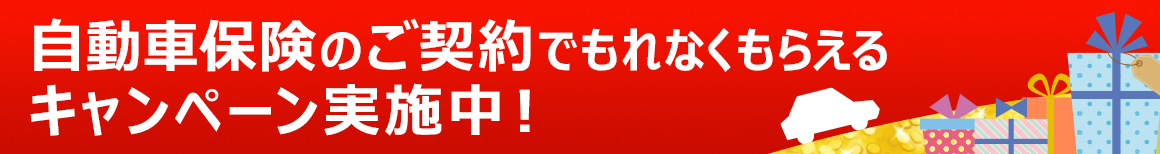保険の基礎知識
医療保険の加入を検討中です。掛け捨て・貯蓄型、どのタイプが良いでしょう?

松本 瑠衣さん(仮名 31歳 会社員)のご相談
今夏、結婚予定です。これまで特に大病もせず元気に過ごしてきましたが、新しい家庭を築くにあたり、医療保険の加入を検討しています。いろいろ探してみると、医療保険は掛け捨てだと思っていたところ、貯蓄型のタイプもあることを知りました。これまで元気だったので掛け捨ては損な気持ちもあるのですが、掛け捨て型と貯蓄型どちらのタイプが良いのでしょうか。
松本 瑠衣さん(仮名)のプロフィール
| 家族構成 | 年収 |
|---|---|
| 本人(31歳 会社員)結婚予定あり | 約450万円 |

鈴木 暁子
(すずき あきこ)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- 掛け捨て型と貯蓄型の違いを理解しましょう。
- ライフプラン、ライフステージによってニーズも違います。
- 保険料はコストと考えましょう。
ライフプランに合わせて保障と貯蓄(資産形成)のバランスを検討しましょう
1.掛け捨て型と貯蓄型の違いを理解しましょう。
松本さん、こんにちは。今夏にご結婚予定とのこと。おめでとうございます。結婚を機に万一の際の保障を検討されるのは大事なことです。ぜひしっかり考えていただきたいです。
医療保険は、一般的には掛け捨て型が多いですが、おっしゃるように貯蓄型のタイプもあります。まずは2つの違いを理解しましょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 貯蓄型 |
|
|
| 掛け捨て型 |
|
|
貯蓄型は「保障と貯蓄の両方を兼ね備えている」のに対し、掛け捨て型は「必要最低限の保障を安く確保できる」という違いがあります。したがってどちらが良い悪いというわけではありません。向いているかどうかで検討しましょう。
貯蓄型保険の特徴に魅力を感じる、あるいは自分のニーズに合っているかどうかでどちらのタイプが向くか向かないかがわかってきます。
- 長期的に医療保障を確保しつつ、貯蓄もしたい(保障と貯蓄の両立)
- 将来、保険を解約して老後資金の一部にしたい
- 当初の保険料が高くても、保険料が変わらず長期的な保障を確保したい
というように、コストよりも安定した手厚さを重視したい人に向いているといえます。
- できるだけ保険料を抑えたい
- 必要な保障を必要な期間だけ確保したい
- ライフステージの変化に応じて柔軟に見直したい
- 貯蓄や資産運用は自分でやりたい
というように、合理的な考え方の人に向いているといえるでしょう。
2.ライフプラン、ライフステージによってニーズも変わります。
30代の女性ですと、結婚をはじめ、出産・育児、キャリア、住宅購入、老後資金準備など、さまざまなライフプランがありますが、ライフプランやライフステージによってもニーズが違うことも意識しておきましょう。先ほどは、一般論として向き、不向きのタイプを挙げてみましたが、松本さんのライフプランにおいて注意すべき事やニーズを考えてみてください。
- 今後のライフイベントが多いので、毎年の家計の収支を良くする事に加え、計画的な資産形成が必要
- 松本さんのキャリアプラン(ご出産後に松本さんが仕事に復帰する《できる》か否か)で世帯収入も変わる可能性がある
- 世代によって必要な保障が変わる可能性もある
など、まだまだ不確定な要素が多いので、できればその時々に応じて柔軟に動けるような状況のほうが楽ではないかと考えます。
資産形成については、毎年の収支バランスをとって、資産形成に回せる資金を捻出できるようにしたいものです。その意味では、ライフプランがあまり固まっていないうちに、固定費となる保険料の負担が大きいと、家計の圧迫につながります。
また、お子さまの成長に伴って教育費がかさむようになるまでは、ご結婚後の家計も資産形成期になります。貯蓄型の保険で貯蓄もという考え方もありますが、貯蓄型保険の場合、保障機能と貯蓄機能があるので、保険料すべてが貯蓄に回るわけではありません。また、運用といってもあくまで保険商品であり、第一義的な目的は万一の保障ですから、保険金額や解約返戻金を減らすようなことがあってはなりません。その意味では、あまりリスクをとった運用はしにくいといえます。
今後まだ十分運用期間もありますので、多少リスクを背負ったとしても積極性も加味した運用を検討しても良いでしょう。その場合、やはりNISAやiDeCOなどの優遇制度を利用して効率的、効果的な運用が望ましいと考えます。
3.保険はモトを取ろうと考えるものではありません。
掛け捨ての保険について、「保険料を捨てているからもったいない」とおっしゃる方が多いのは事実です。ただ、保険というのはそもそも「確率は低いけれど、万一発生したら経済的負担が大きいという突発的な事態」に備えるためのものです。発生の確率が低いのであれば、最低限のコストで済ませるというのが掛け捨て型の保険料です。
一方で、万一の事態であっても長期的に保障してくれる。さらに最も効率的とは言えないまでも適度なリスクと適度なリターンの運用を自分に変わってやってくれるのであれば、その分手数がかかるので保険料が割高になるのは当然です。
ですから、松本さんも、保障と貯蓄(資産形成)の使い分けをどのように考えるのか、そしてそのためにどの部分にコストをかけ、どの部分のコストは抑えるといったメリハリを、今後のライフプランに照らし合わせながら検討してみてください。そのような視点で選べばご自身のニーズと保険商品がアンマッチということにはならないと思います。

| 執筆者 | 鈴木 暁子 (すずき あきこ) |
|---|---|
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。企業、自治体などで講演活動を行う一方、執筆やメディア取材協力での情報発信、個人相談など精力的に活動中。ライフスタイルが多様化する今、その人らしいライフプランづくりを応援するFP。資産形成、リタイアメントプランニング、高齢期の住まいとお金のサポートを得意とする。武蔵大学経済学部非常勤講師、J-FLEC認定アドバイザー。 |