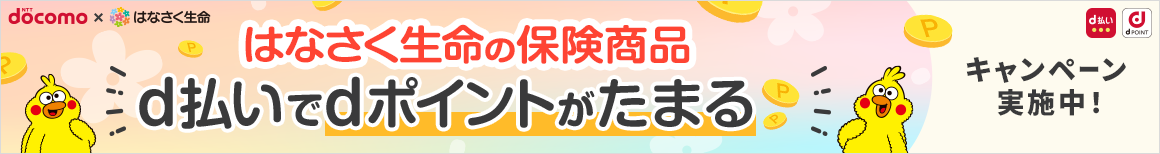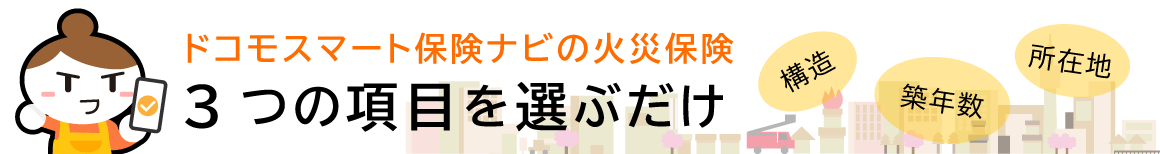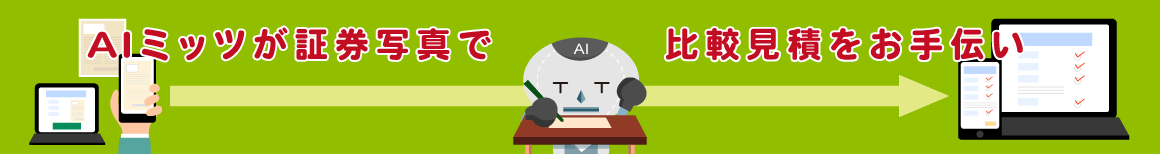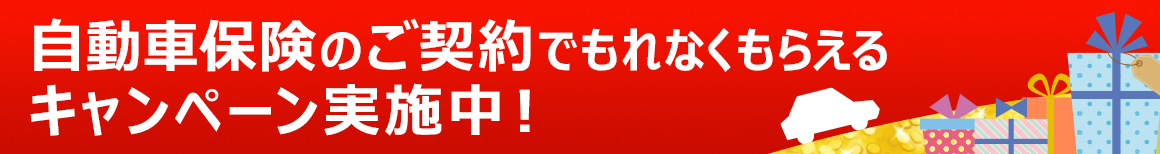保険の基礎知識
医療保険は不妊治療でも給付対象になるのでしょうか?

佐藤 遥さん(仮名 30歳 会社員)のご相談
なかなか子宝に恵まれず、いずれ不妊治療も考えなければならないと思っています。しかし、その金銭的負担がとても心配です。医療保険では、不妊治療でも給付金は出るのでしょうか? また保険以外に、不妊治療の金銭的な負担を軽くする手段はあるのでしょうか?
佐藤 遥さん(仮名)のプロフィール
| 家族構成 | |||
|---|---|---|---|
| ご相談者 | 佐藤 遥 さん | 30歳(会社員) | 手取り年収 250万円 |
| 配偶者 | 拓哉さん | 32歳(会社員) | 手取り年収 250万円 |
| 貯蓄額 | 300万円 |
|---|

村井 英一
(むらい えいいち)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- 多くの不妊治療が、公的医療保険の対象になりました
- 自由診療は、保険商品によって扱いが異なります
- 自治体や勤務先、健保組合で支援がないか、確認しましょう
公的医療保険の対象となる不妊治療は、保険会社の医療保険でも対象となります
1.まずは公的医療保険の対象となるか、確認をしましょう
不妊治療は、大きな費用負担がかかるイメージがあります。経済的な負担に耐えかねて不妊治療を諦めたという話を聞くこともありました。実際のところはどうなのでしょうか。
保険会社が扱う医療保険で不妊治療に給付金が出るのか、という点が今回のご質問の趣旨です。しかし、その前に公的医療保険、つまり健康保険や国民健康保険、共済組合による給付から考えてみましょう。
2022年4月1日から、多くの不妊治療に公的医療保険が適用されることとなりました。具体的にはタイミング法、人工授精、体外受精などです。自己負担は実際にかかった医療費の3割です。以前は全額自己負担でしたので、「不妊治療は費用負担が大きい」というイメージがありましたが、保険適用になったおかげで負担はずいぶんと軽減されました。それでも自己負担が10万円以上かかる場合もありますが、その場合は公的医療保険から高額療養費が給付されます。所得によっても変わりますが、1か月の自己負担はおおむね8~9万円程度で抑えられます。
公的医療保険が適用されない不妊治療もあります。いわゆる「自由診療」と言われるものですが、この場合は全額が自己負担となります。さらに、保険適用外の治療だけでなく、その治療にかかわる基礎的な医療費も含めて、すべてが自己負担となってしまいます。
保険適用外の治療の中でも、「先進医療」として認められた治療を、厚生労働省に届け出た医療機関で受ける場合は、保険外併用療養費が給付されます。保険適用外の治療については全額自己負担となりますが、それ以外の基礎的な医療には保険が適用され、3割負担となります。
このように、不妊治療といっても、治療法により自己負担は大きく異なります。安全性や治療効果はもちろん、経済的な負担も考慮しながら、治療法を選択する必要があります。
2.公的医療保険が適用される手術には手術給付金が出ます
公的医療保険の扱いに差があることを踏まえた上で、保険会社が扱う医療保険での扱いを見てみましょう。
まず、公的医療保険の対象となる治療は、保険会社の医療保険ではほとんどが給付の対象となります。金額や給付条件の詳細は保険商品によって異なりますが、入院をすれば入院給付金、手術をすれば手術給付金が支払われるのが一般的です。不妊治療の場合、入院はしないことが多いので、手術給付金が主な対象になるでしょう。公的医療保険の適用対象が広がったことで、保険会社の医療保険の対象も増えました。
先進医療の場合、保険会社の医療保険では先進医療特約に加入していると、給付金が支払われます。先進医療特約の保険料は月額数百円程度ですが、費用の全額が賄われるものも多く、経済的な負担の助けになります。
自由診療の場合は、治療法によっては給付金が出る保険商品もあります。その扱いは保険商品によってまちまちですので、個別に確認する必要があります。その場合には、具体的な治療法の名前を言って問い合わせることが大切です。治療法によって、扱いがまったく異なるからです。
このように、保険会社の医療保険での扱いは、公的医療保険の扱いに準じて異なります。また、同じ自由診療でも扱いはまちまちですので、加入に当たっては十分な確認が必要です。さらに不妊治療をしていると、どこまで資金を投じるか、という大きな問題にも行き当たります。ご夫婦でもよく話し合って、二人にとって適切な方法を選択することが大切になります。
3.治療費が10万円を超えたら、医療費控除の対象になります
自治体によっては、不妊治療を支援するところもあります。最近では少子化を防ぐために、費用の一部を助成する自治体が増えています。お住まいの自治体で実施していないか、調べてみるとよいでしょう。例えば、東京都では(2025年5月現在)、保険診療と合わせて実施した先進医療に係る費用の一部を助成しています。自治体の支援制度は、自治体ごとに内容が異なります。申請期限が限られていたり、予算に達した時点で打ち切りとなる場合がありますので、こまめに情報を確認する必要があります。
お勤め先で福利厚生制度の一環として支援制度を設けている場合もあります。また、加入している健康保険組合に独自の支援制度が設けられていることもあります。不妊治療が支援メニューの対象になっていないか、一度確認してみるとよいでしょう。
1年間の医療費が高額になった場合は、医療費控除の対象になります。不妊治療に限らず、年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えたら、その分を所得から差し引いて税額が計算されます。その結果、所得税や住民税が減税となります。不妊治療は自己負担が大きいことが多く、医療費控除を活用したいものです。
このような制度も活用して、不妊治療の負担を抑えたいものです。

| 執筆者 | 村井 英一 (むらい えいいち) |
|---|---|
| Webサイト | https://kakeinoshindan.com/ |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大手証券会社で長年、資産運用の相談を受けた。ファイナンシャル・プランナーとして独立後は、家計診断、保険の選択、住宅ローンなどで、多くのお客様からのご相談を受ける。シミュレーション分析を得意としており、20年後、30年後の家計の状況を推測して提案を行う。また、全国各地で家計管理に関する講演を行っている。 |