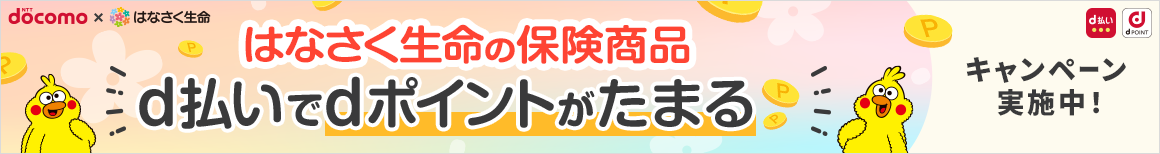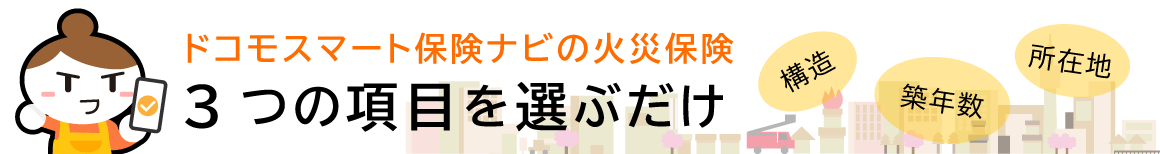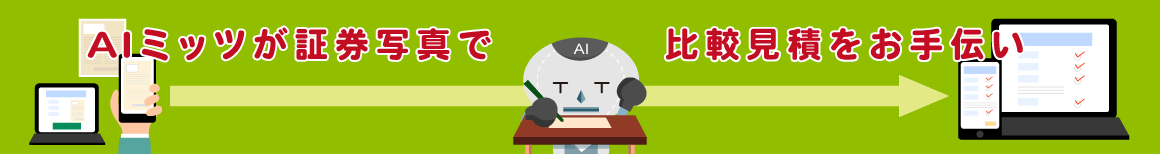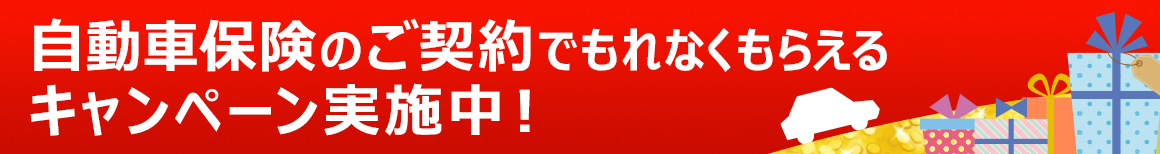保険の基礎知識
生命保険料の払込期間は、「終身払込方法」と「60歳等で払い込みが満了する方法」のどちらが良いの?

遠藤 美香さん(仮名 30歳 会社員)のご相談
子の誕生に伴い夫婦の保険の見直しを検討し、新たな保険に追加で加入することを決めました。
ただ、一生涯保障が続く保険の場合、保険料の払込期間には「終身払込方法」と60歳や65歳等で払込が満了する「短期(有期)払込方法」とがあり、どちらの払込期間のコースかを選べると言われました。保険ショップからのお勧めコースの提案も受けましたが、その選択で良いのか自分達では判断がつきません。
どのように考えていけば良いのでしょうか。中立公平な立場から教えてください。
遠藤 美香さん(仮名)のプロフィール
| 職業・年収 | 貯蓄額 | 新規で提案され加入を検討した保険 | |
|---|---|---|---|
| 本人(30歳) |
|
2,400万円 |
|
| 夫 (30歳) |
|
||
| 長男 (1歳) | - |

井上 信一
(いのうえ しんいち)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- 保険料払込期間の有利な選択に答えはありません
- いつまで必要な保障であるかを考えることは選択の際の参考になります
- 保険商品の種類等に応じ、大まかな選び方を検討することもできます
表面的な保険料の多寡だけでなく、保障が必要となる期間や、保険商品の商品性なども考慮して、相性の良い払込方法を考えましょう。
遠藤さま、ご相談ありがとうございます。
新規加入を検討されている終身保障の生命保険や医療保険等について、保険料払込期間の選択の考え方ですね。
まず、万一のことがあった場合に得られる保障と、その対価としてそれまで負担してきた既払込保険料。どういった払込方法が有利かは、将来のいつ起こるか予測できない事故によっても変わるので、何が正解なのかを断定することはできません。別の視点からの選択も考慮しましょう。
払込期間の違いによるメリットとデメリットは単純ではない
保険の保険料払込期間について、保険期間と払込期間が同じものを「全期払い」、保険期間より払込期間が短いものを「短期(有期)払い」といいます。
保険期間が一生涯続く「終身保障」の保険の場合、「全期払い」とは「終身払込方法」であり、生涯に渡り保険料の支払いが続きます。一方、「短期(有期)払い」では60歳や65歳等の所定年齢で保険料の支払いが終わります。すべての保険会社で2つの払込方法があるという訳ではありませんが、もし、選択できるとしても選ぶのは中々に悩ましいところです。
保険商品によってやや考え方が異なりますし、保険金額が高額の場合に受けられる割引制度などでイレギュラーな場合もあります。ですが、基本的なしくみとして、保険会社は人の一生が何歳までなのかをひとまず仮定し、どの払込方法でもその間に払い込まれる保険料の総額が等しくなるように、毎月等の保険料を計算します。
このことから、払込期間の違いによるメリットとデメリットは、次のような相反関係となります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 終身払込方法 | 毎月等の保険料が相対的に安い | 保険料負担は一生続く |
| 短期(有期)払込方法 | 保険料負担は所定年齢で終わる | 毎月等の保険料が相対的に高い |
また、この理屈のもと、実際の保険料を試算し比較すれば、次のように保険会社が「人の一生は何歳まで」と考えているのかを推測することができます。
終身保険(万一の際に死亡保険金が支払われる生命保険)の月払い保険料の比較
| 30歳男性 | 30歳女性 | |
|---|---|---|
| 終身払込方法 | 11,700円 | 10,150円 |
| 60歳払込満了方法 (保険料払込期間30年)/損益分岐余命年数 |
19,360円(6,969,600円) /約49.6年 |
18,320円(6,595,200円) /約54.1年 |
出典:同一の保険会社による保険料試算をもとに筆者作成
表中の保険料は、保険会社により異なりますし、同じ保険会社であっても契約する保険金額の多寡により複雑です(例えば1,000万円で契約する場合の保険料が、単純に200万円で契約する場合の5倍とはならない場合もあります)。あくまでも参考の一例としてください。
さて、この例で30歳男性が1,000万円の終身保険に加入する場合、「終身払込方法」での月払い保険料は11,700円となっています。保険料の払い込みは被保険者が亡くなるまで続くので、払込総額は計算できません。
一方、60歳までの30年間の「短期(有期)払込方法」の月払い保険料は19,360円なので、払込保険料の総額は、6,969,600円(19,360円×12か月×30年)と計算できます。
この払込保険料総額を「終身払込方法」での月払い保険料で除すると、2つの払込方法の違いによる損益分岐を計算することができ、この場合では約49.6年となります(6,969,600円÷12か月÷11,700円)。
これは、30歳男性の余命年数を49.6年(一生は79.6歳)とみなして保険料を設定していると考えられます。同様に計算すると30歳女性の余命年数は54.1年(一生は84.1歳)となります。
つまり、毎月の保険料が安くても、男性の場合では80歳を過ぎて保険料を払い続けると、「60歳払込満了方法」の場合より払込保険料総額が多くなってしまうということを表しています。
ちなみに、厚生労働省が発表している簡易生命表では、令和6年度の30歳男性の平均余命は51.71年、女性の平均余命は57.67年なので、保険会社の設定の方がやや厳しめ(余命年数が短め)としていることがわかります。
しかし、将来の出来事を予測することはできません。人の寿命も、いつどんな病気に罹ってしまうのかどうかも、予想できません。保険はあくまでも大数のデータをもとに数理計算するので、契約者・被保険者の個々の状況などは、まさに終わってみなければわからないということ。
よって、どちらの払込方法が良いのかという問いへの正解は無いのです。
それでも強いてあげれば、複数の保険会社の保険料を比較し、明らかに損益分岐余命年数が他社の同タイプの保険と比べて異質なら、終身払込方法または短期払込方法のどちらかが相対的に割安に設定されているという可能性があるかもしれません。
その保険は一生必要なのか?将来、解約をする可能性はないか?
保険を検討する際には、保険商品ありきではなく、日常生活におけるリスクとその保障の必要性から考えるのが大切です。この場合の保障の必要性とは、準備すべき「保障額」と「保障期間」を検討することになります。
例えば、子のような扶養家族のある生計者(夫婦で働いていれば二人とも)の「死亡保障」については、扶養家族の年齢に伴い、概ね必要な保障額は逓減します。よって、定期保険特約等で準備する高額な保険金を次第に減らし、子の経済的独立後の保障期間は不要であると考えることは理に適っています。
一方、終身保険は保険料こそ高いものの、やがて解約返戻金の額が払込保険料総額を上回るしくみです。このため、必要に応じて一部を解約して様々な使途に充てることができるほか、いつか訪れる自分の死により支払われる保険金は、遺された家族にとって、先行き不透明な老後資金等の大切な財源となり得ます。預貯金等の他の金融資産が相当に潤沢であるか、余程の事情が無い限り、既契約の終身保険は全部を解約せず継続するのが無難といえます。
高齢期のお金の不透明性を考える場合、いつまで要介護の状態が続き、どれくらいの自己負担額がかかるのかが不透明な「介護保障」にも同様のことがいえるかもしれません。
しかし、いつかは誰でも亡くなるため、その当事者となる「死亡保障」とは異なり、「介護保障」や「医療保障」については、保険商品による保障が必要となる当事者とはならない可能性もあります。また、就労中の現役世代は、病気やケガが原因で支出が増えるリスクだけでなく収入の減少や途絶といったリスクをも考えねばなりませんが、リタイヤ後の老後は少なくともケガや病気が原因で収入(年金)の減少・途絶が生じるわけではありません。ある程度の金融資産があれば、なんとかカバーすることも可能でしょう。
たしかに、加齢に伴い医療や介護に関わる危険性は増すでしょうし、患う病気の種類等によっては高額の支出が続き、家計を窮地に陥れてしまう可能性も否めません。しかし、備えるべきリスクの深刻度から優先順位を考えておき、全てを保険で準備するのが難しくなった際には取捨選択もやむを得ないこともあります。
唯一の正解ではなく、数ある考え方の1つに過ぎない
このように保障が必要となる期間から考えた場合、一生涯に渡り付き合う保険は、収入の減る高齢期の負担をなくすためにも「短期(有期)払込方法」で検討する。逆に、将来はどこかで解約してもそれほど深刻な状況にはならないような保険は、必要な期間分を比較的割安な「終身払込方法」で検討する。こうした発想も、ひとつの考えではないかと思います。
ちなみに、上記の終身保険と同じく30歳の男女のケースで、終身医療保険と終身がん保険の場合の保険料(入院給付金を1万円とする場合)を試算すると、終身医療保険は男女とも損益分岐年数が終身保険より長い(男性:約59年、女性:約61年)、終身がん保険は男女とも短い(男性:約45年、女性:約46年)結果となりました。
全ての保険会社の試算をしたわけではありませんし、契約時の年齢により異なる可能性もあります。また、あくまでも終身保険(死亡保障保険)と比較した場合に過ぎませんが、終身医療保険では人の一生を概ね長く見積もる傾向があるといえ、相対的には「終身払込方法」での保険料を「短期(有期)払込方法」より割安に設定しているケースもあるといえそうです。
一方、終身がん保険はその逆で、「短期(有期)払込方法」の方が相対的にはやや割安な場合もあるといえそうです。
保険の商品性による違いも選択基準となり得る
最後に、加入を検討している保険商品の商品性から「払込方法」をチェックするポイントを考えます。
結論からいえば、以下のような特徴を持つ保険商品の場合は、「短期(有期)払込方法」を選んでおくのが無難といえそうです。
① 保障内容移行制度が約款で認められている終身保険
② 低解約返戻金型の保険
上記は、いずれも、主に死亡保障保険である終身保険に該当することが多いケースとなります。
一般的に、終身保険では「所定」時期に、死亡保険金の一部または全部を年金受取や介護年金受取に変更できる「保障内容移行制度」の機能があります。また、「低解約返戻金型」保険の場合、「所定」時期までの「低解約返戻適用期間」中の解約返戻金は低く抑える代わりに保険料を割安にし、「所定」時期経過後は解約返戻金の制限を解きます(低解約返戻適用期間経過後は解約返戻金が増えます)。これらに該当する「所定」時期とは、「保険料払込満了時」とするのが一般的であり、「短期(有期)払込方法」に特有のしくみといえます。
逆に、以下のような場合は、「終身払込方法」を選んでおくのが無難といえます。
③ 保険料払込免除特約が付加されている、または付加可能な保険
④ 保障額や保障内容が将来的にも適正であるかが不透明である保険
特に、がん保険では初めてがんと診断確定された場合、介護保険では初めて所定の要介護状態と認定された場合、それ以後の保険料の払い込みを免除する特約が自動付帯される保険もあります。仮に自動付帯されていない場合でも、追加特約料を負担して、任意で保険料払込免除特約を付帯すれば、がんと闘っていく際や要介護状態となった際の負担軽減の面で安心といえるでしょう。
所定の状態となれば以後の保険料の支払いはなくなるのですから、保険料払込免除特約の特約料の負担が加わる分だけ、ベースとなる保険料は少しでも割安な「終身払込方法」が、比較的相性が良いと考えることもできます。
一方、とくに医療保険やがん保険の分野で該当することですが、医療技術が目まぐるしく発展する昨今、いま契約する保障内容や保障額が、将来的に陳腐化してしまわないかも慎重に考えておきたいところ。
例えば、従来型の医療保険とは異なり、昨今では入院・手術給付金の保障額を自分で設定するのではなく、診療報酬点数に連動するタイプや実際に費やした実費に連動するタイプも増えています。がん保険では、がんでの入院日数の短期化を受け、従来の入院保障重視ではなく、入院の有無に関係なく診断時や治療時の保障を重視する保険が主流となっています。
この先も医療環境の変化に応じて多様な保障を謳う新しい保険が登場してくるでしょう。こうした保障内容に変化があり得るリスクに対しては、定期保障タイプか、終身保障タイプの保険であっても、適宜乗換えのしやすい「終身払込方法」を選んでおくのも1つの考え方でしょう。
冒頭でも述べたとおり、異なる「保険料払込方法」での有利不利を一概に決めることはできませんし、今回紹介した損益分岐年数の理屈も机上の計算に過ぎません。
必要となる保障期間や保険の商品性なども、検討材料に加えて考えていきましょう。

| 執筆者 | 井上 信一 (いのうえ しんいち) |
|---|---|
| Webサイト | https://www.shinichi-inoue.com/ |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大学卒業後、大手メーカーでの業務の中でライフプランの必要性を肌で感じFPとなる。以後、FP教育会社、リスクマネジメント会社のFP部門を経て2010年に独立開業。年間約100件の相談、約500時間の講師業のほか、企業の福利厚生相談、執筆・監修等にも従事。「最終的にお客様が選ぶ道は1つでも、FPの付加価値としていかに多角的な発想や選択肢を提案できるか」を信条としている。成年後見人として地域福祉への貢献活動もおこなっている。 |