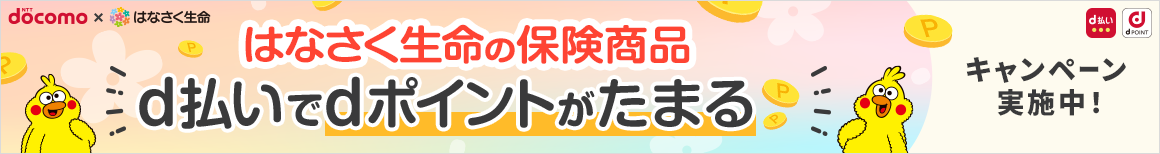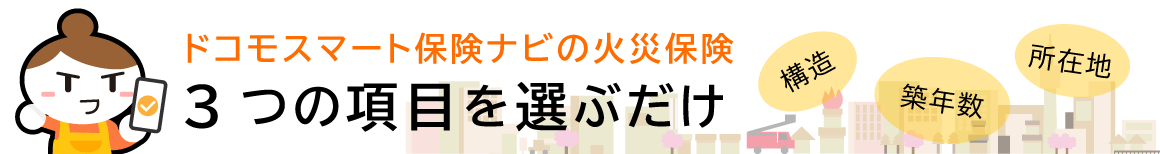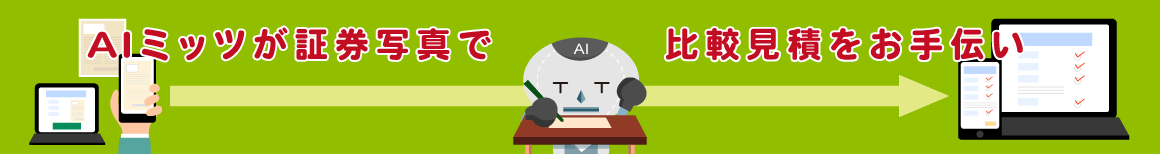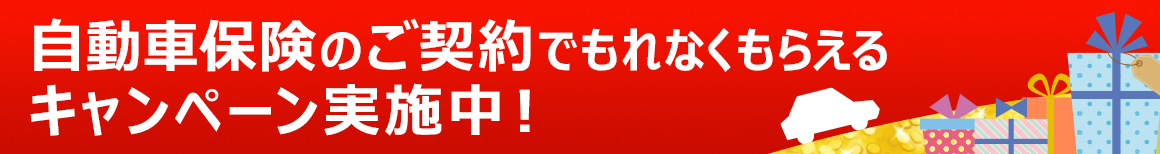相続
実家の土地と建物を相続しましたが、はっきり言って要りません

小林 哲也さん(仮名 54歳 会社員)のご相談
1年前に母親が亡くなり、実家の土地と建物を相続しました。しかし、私はすでに今の住まいを購入していますし、今後郷里に帰るつもりはありません。私にとってはまったく必要ない不動産ですので、相続の登記もしていません。実家の場所はかなり辺鄙な場所で、資産価値はほとんどありません。それでも固定資産税を払い続けなければならないのでしょうか?
小林 哲也さんのプロフィール
| 家族構成 | ||
|---|---|---|
| 家族 | 年収 | |
| ご相談者 | 小林 哲也 さん 54歳(会社員) | 手取り年収 580万円 |
| 妻 51歳(パート主婦) | 手取り年収 95万円 | |
| 長男 17歳(高校2年生) | - | |
| 貯蓄額 | 1,800万円 |
|---|

村井 英一
(むらい えいいち)先生
ファイナンシャル・プランナーからの
アドバイスのポイント!
- 相続登記が完了していなくても、固定資産税の支払いは必要です
- 相続土地国庫帰属制度の対象になるには、建物を取り壊す必要があります
- 田舎暮らしにあこがれる人が買い手となることが期待されます
相続土地国庫帰属制度が創設されましたが、まずは売却できないかを探りましょう。
1. 相続した不動産が負担になることも...
「実家の不動産を相続したくない」というご相談は増えています。若い頃に郷里から東京や大阪などの大都市に出てきて就職し、そのまま都市部に住み続けた人は多くいます。すでに都市部でマイホームを購入しており、郷里に戻ることもない人が少なくありません。そのような人にとっては、郷里の不動産を相続しても負担になるだけでしょう。ご自身が育った場所ではありますが、ご近所との交流は少なくなり、ご両親が亡くなれば、帰省することもなくなります。しかし、そのような土地であっても、いったん相続すれば、毎年固定資産税の納税通知書が送られてきて、支払いをしなければなりません。雑草が生い茂り、建物が朽ち果てて近隣に迷惑をかけないよう、維持管理をする義務も生じます。年に数回、雑草取りのために泊りがけで帰省しているという人もいます。また、ご近所の方にお金を払って管理してもらっているという話も聞きます。
地方でも、比較的需要がある地域であれば売却することもできますが、かなり山奥で、人里離れた場所のため買い手が見込めず、〝売るに売れない〟とやむなく保有し続けている人は少なくありません。
2. 2024年から相続登記が義務になりました
「相続の登記をしていない」とのことですが、2024年4月から、相続登記が義務化されました。「相続したことを知った日」あるいは「遺産分割が成立して相続した日」から3年以内に相続登記をして、不動産の名義を変更しなければなりません。以前は義務ではありませんでしたので、不動産の登記が亡くなった親のまま、あるいは祖父母のまま放置されているというケースもありますが、今後はそうはいきません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した場合でも、3年の猶予期間がありますが、相続登記義務の対象になります。
また、購入希望者が現れた際に、相続登記が完了していなければ売買ができないということにもなりかねません。売却のチャンスを逃さないためにも、早めに相続登記の手続きをした方がよいでしょう。
ちなみに、相続登記が完了していなくても、固定資産税の納税通知書は相続人の代表者のもとに送られてきますので、税金の支払いは毎年必要になります。
3. 相続土地国庫帰属制度が創設されました
相続3か月以内であれば、家庭裁判所に申し出て、相続放棄をすることもできます。この場合は、不動産だけでなく、すべての財産の相続を放棄する必要があります。相続人のすべてが相続放棄をすれば、いくつかの手続きを経て、亡くなった方の財産は国庫に納められます。小林さまの場合、すでに1年が経過していますので、この手続きは取れません。
ただ、「相続した不動産が必要ない」という人のために、土地を国庫に納める「相続土地国庫帰属制度」が昨年(2023年)4月から始まりました。相続で取得した土地を国が引き取ってくれるという制度です。そうすることで、固定資産税の支払いや管理の負担から逃れることができます。土地は相続したものに限られますが、相続した時期に限定はありません。例えば数十年前に相続した土地でも対象になります。ただし、いろいろな条件に適合した土地に限られます。以下のような土地は対象になりません。
① 建物がある土地
② 担保などの権利が設定されている土地
③ 有害物により汚染されている土地
④ 崖があるなど、管理に費用がかかる土地
⑤ 工作物や車両など、除去が必要なものが地上や地下にある土地
そのほか、細かい条件がいろいろとあります。いずれも法務局に申請して、審査を受ける必要があります。審査手数料14,000円と、10年分の土地管理費相当額の負担金(宅地の場合20万円~)の費用が必要です。国が買い取ってくれるわけではないので、売却代金は受け取れません。
小林さまの場合、まず建物を取り壊す必要があり、この制度を利用するのにも少なくない費用がかかります。ご実家の場所や建物の状態など詳しい状況がわかりませんので、何とも言えませんが、まずは売却の可能性を探ってみることをお勧めいたします。最近は田舎暮らしを望む人も増えており、価格を問わなければ購入希望者が現れる可能性もあります。
また、自治体で「空き家バンク」の登録を行っている場合があります。登録されると自治体のホームページなどで公開されますので、田舎暮らしにあこがれる都会の人の目に留まりやすくなります。「こんなに不便な場所が...」とデメリットに思うことを魅力と感じる人もいます。
もちろん、すぐに買い手が現れるとは限りませんので、それまでは物件の管理と固定資産税の支払いが必要になります。それでも、あきらめずにいろいろな可能性を探っていくとよいでしょう。

| 執筆者 | 村井 英一 (むらい えいいち) |
|---|---|
| Webサイト | https://kakeinoshindan.com/ |
| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。大手証券会社で長年、資産運用の相談を受けた。ファイナンシャル・プランナーとして独立後は、家計診断、保険の選択、住宅ローンなどで、多くのお客様からのご相談を受ける。シミュレーション分析を得意としており、20年後、30年後の家計の状況を推測して提案を行う。また、全国各地で家計管理に関する講演を行っている。 |